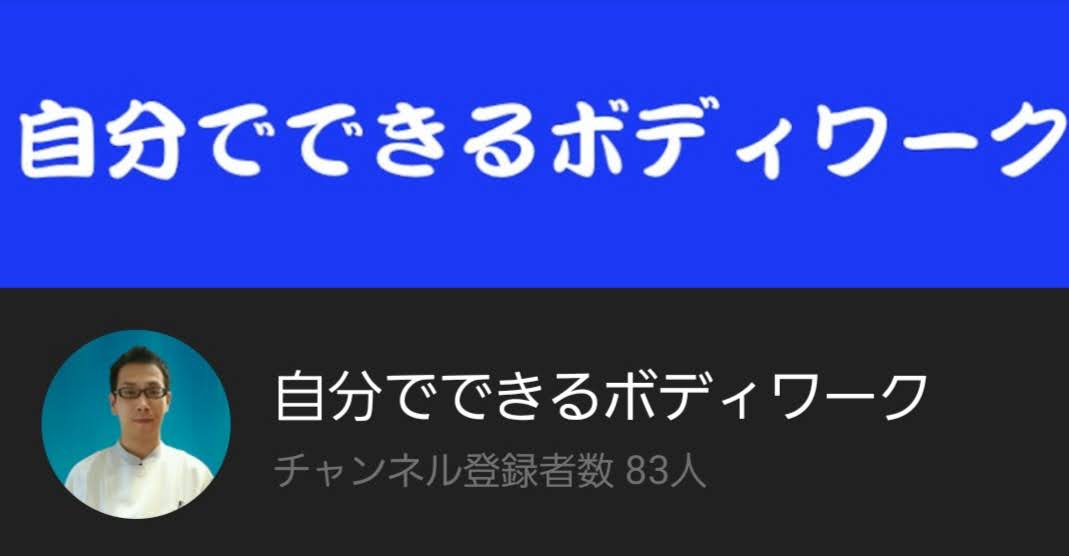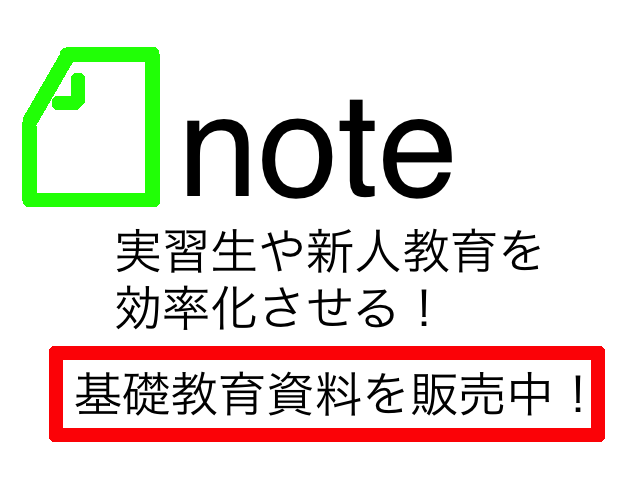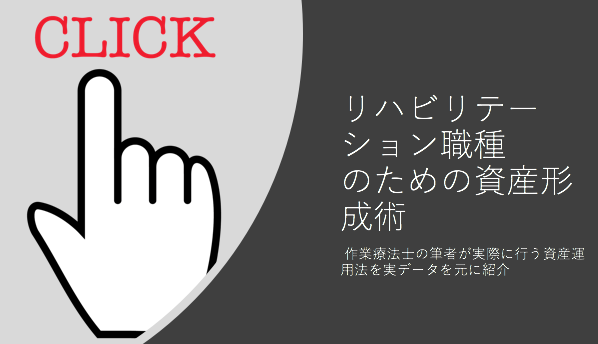腰痛を発生させる原因となる筋肉には、いくつか考えられます。今回、腰痛の原因となるトリガーポイントと、予防・改善のためのストレッチとトレーニングについてまとめていきたいと思います。
目次
腰痛発生の原因筋とトリガーポイント、腰痛予防・改善のためのストレッチとトレーニング
スポンサードサーチ
参考文献
スポンサードサーチ
腹直筋のトリガーポイントと腰痛予防・改善のためのストレッチとトレーニング
服直筋について
腹直筋は主に第5〜7肋骨の外側面に付着し、恥骨の上に向けてまっすぐ走行しています。
3〜4本の腱画という横に走る腱のすじがあり、縦に走る白線で左右に分割されます。
この縦と横の線により、いわゆる「腹筋が割れている」状態が成り立ちます。
腹直筋は前屈の補助や上体を起こしたり、上体を丸めるなどの腹筋運動で働きます。
直立姿勢で背筋とともに安定性を作り、平地に比べて上り坂を歩くときの方が負荷は大きくなります。
背筋の収縮時には、咳や排便などの活動をサポートする役割があります。

出典:誰でもできるトリガーポイントの探し方・治し方 腰痛
腹直筋のトリガーポイントと関連痛
腹直筋のトリガーポイントはどの部分にもできますが、腰痛に関連する部位としては腱画の下部で恥骨のすぐ上の部分で形成されやすくなります。
ここにトリガーポイントがあると、腰全体や臀部、仙腸関節にも関連痛を送り、尿道括約筋の痙攣の原因にもなります。片側のトリガーポイントでも腰全体に痛みが生じます。
臍の横で少し下がった部分のトリガーポイントは虫垂炎に似た痛みで、月経前症候群や重度の月経痛、動くと悪化する腹部の痛みの誘因となりえます。
胸郭の内縁で、腹直筋と胸郭との付着部のトリガーポイントは、中背部全体の横に走る痛みを引き起こし、場合によっては胸焼け感を生じさせることもあります。

出典:誰でもできるトリガーポイントの探し方・治し方 腰痛
腹直筋が悪化する原因とトリガーポイントが疑われる症状
悪化する原因
・過度な腹筋運動
・強いストレス、緊張
・排便や出産時の負荷
・手術による組織損傷
・不適切な前傾姿勢での荷物の持ち上げ
・腹部の脂肪が多く、体幹の可動域が制限される
・腹部の慢性的な締め付け(お腹を引っ込める動作)
・締め付けすぎるベルトなど
トリガーポイントが疑われる症状
・腰全体の痛み
・腹部の筋力低下
・体幹関節可動域制限
・重度の月経痛
・胸焼け感
・腹部の痛み
・深呼吸をしたときの痛み
腹直筋の評価
触診テスト
仰向けで背中を伸ばし、恥骨の上から上方に順次指で腹直筋を押します。周辺よりも硬い部位、こわばりがある部位、押したときに背部などの痛みが生じる部位を確認します。
上体倒し
膝を曲げて床に座り、できれば足を上から押さえれれる環境で行います。
できるだけリラックスした状態で、10秒かけて状態を後ろに倒していきます。
痛みなくゆっくりと倒すことが可能であれば服直筋に問題はないと考えます。痛みが強すぎてゆっくりと倒せなかったり、運動中に腹直筋に痙攣が起こるようであればトリガーポイントの存在が疑われます。
上体起こし
膝を曲げて床に座り、できれば足を上から押さえれれる環境で行います。
頭上に手を伸ばしてから、腕を前へスイングさせながら上体を起こしていきます。
上体を起こせなかったり、痛みが生じる場合腹直筋にトリガーポイントの存在が疑われます。
トリガーポイントを示唆する姿勢チェック
立位姿勢
・前傾姿勢orうつむきがちの姿勢
・腕や手の内旋
・腰椎前弯減少
・腰部の過剰な湾曲or腹部突出
・肋骨前面の下方への引っ張りと中背部の丸み姿勢
・肩と胸が同時に動く呼吸
座位姿勢
・背中を真っ直ぐ伸ばして座ると疲労しやすい
・すぐに前傾姿勢で肘を机や膝につく
・うつむきがちの姿勢
・猫背の方が楽
・背中が反り気味
歩行姿勢
・前傾姿勢
・うつむきがちの姿勢
・歩幅が狭い
・骨盤が固定されたまま
これらのうち当てはまる項目があれば、腹直筋の慢性的な硬さや、その他の筋の慢性的なこわばった筋の存在が示唆されます。
腹直筋のトリガーポイントに対する治療の考え方
座位時間が長い方の場合、腹直筋のトリガーポイントが複数存在し、慢性的に腹直筋が収縮している場合があります。この時には筋全体の緊張を緩和する必要があります。
腹直筋治療では、背中の傍脊柱筋(脊柱起立筋、多裂筋、回旋筋など)のストレッチも行うとより効果が期待できます。
これは、腹直筋をストレッチすると背部の筋が収縮するので、その後背中の筋をストレッチすることが望ましくなるためです。
腹直筋のストレッチ後には、例えばチャイルドポーズ(正座で体幹を大腿前面につけ、額を床につけ、腕を伸ばす)を数回行うようにします。
腹直筋のトリガーポイントに対する治療法:圧迫
腹直筋が硬くこわばりがある場合、まずはホットパックで温めたり、風呂に入り体を温めることが有効になります。
仰向けでの圧迫
恥骨のすぐ上から始め、指で腹直筋を押しながら上方へ圧迫していきます。痛い部位や硬さのある部位を探しながら、両側の腹直筋を下から上へと圧迫していきます。
問題のある部位が見つかったら、10秒程度押圧します。またその部位の皮膚をつまみ上げ組織を剥がすようにすることも有効です(皮膚と筋膜のリリース)。
側臥位での圧迫
腕や枕で頭部を支え、ローラーを臍に向かって当てます。そこからゆっくりと不快感がない程度に体重を預けていきます。痛みや硬さのある部位があれば、10秒程度圧迫をします。ローラーを移動させながら腹直筋上部まで治療していきます。
うつ伏せでの圧迫
うつ伏せでローラーを左右どちらかの恥骨の部分に当てます。同じ側の肘に体重をかけ、対側の脚は曲げておきます。こうすることで、体重のかけ方をコンントロールできます。
体を下にずらしていき、ローラーを胸郭まで移動させていきます。
両脚を真っ直ぐにして恥骨部分の腹直筋に当てる方法もあります。

圧迫用ローラー
私は、筋膜リリースに有効なランブルローラーを使用しています。

腹直筋のトリガーポイントに対する治療法:ストレッチ
立位でのストレッチ
図のように、戸口を利用したストレッチです。
これにより体幹前面筋が伸長されます。10秒間静止し、脚を代えて同様に行います。

コブラポーズ
このポーズは負荷が高いため、腰痛があまり感じなくなるレベルの方向けとなります。
最初はうつ伏せで胸の下にクッションを徐々に高くして置いていくところから始めていきます。この時背筋と腹直筋はリラックスさせておきます。
次に自動的なストレッチに移ります。うつ伏せで手を肩の真下に置き、肘がまっすぐ伸びるまで体幹を起こしていきます。腹直筋と背筋は弛緩させ、10秒程度静止してから体を元に戻していきます。

腹直筋のトリガーポイントに対する治療法:コントラクト・リラックス
コントラクト・リラックスは、抵抗を利用した動作(収縮)と弛緩を交互に繰り返すことで可動性を高めていくものです。
ストレッチとコントラクト・リラックスを交互に行うと、より効果が期待できます。
座位での腹直筋収縮
椅子に座り、胸に自分の両手を当てます。手は背中の方向に押し、それに抗するように腹部を収縮させます。10秒収縮させ、弛緩させます。
次に傍脊柱筋の収縮のために、椅子の背もたれに対して体幹上方を後ろに押し付けます。10秒収縮させ、弛緩します。
上体倒し
膝を曲げて床に座り、できれば足を上から押さえれれる環境で行います。
できるだけリラックスした状態で、10秒かけて状態を後ろに倒していきます。
上体倒しが終われば、仰向けのまま弛緩し、腕を頭上に伸ばし10秒程度ストレッチさせます。
腹直筋のトリガーポイントに対する治療法:トレーニング
骨盤前後傾運動
座位で息を吸いながら腹筋をリラックスさせ、腹部をゆっくりと前に突き出しながら骨盤を前傾させます。
息を吐きながらゆっくりと腰を後ろに突き出しながら腹部を引き骨盤を後傾させます。
立位でも同様に行います。
余裕があればフィットネスボール(バランスボール)上でも行います。
スレッドザニードル
四つ這いで頭頸部、体幹を右に回旋させ左手は胸の下を通り右に伸ばします。

左腕を抜き、頭頸部、体幹を左に回旋させながら天井に上げます(視線は指先)。

負荷をかける場合は、動かす手に重りを持たせると良いです。
体幹屈曲・伸展エクササイズ
初級
膝を伸ばして立ち、両手を後ろ回します。背中を伸ばしながら股関節から屈曲し、ゆっくりと最初の姿勢に戻ります。痛みを感じない範囲で行い、90度前屈できるようになるまで行います。

最初の姿勢から、両手を腰に当て、体幹をゆっくりと後ろに反らしていきます。ゆっくりと元の姿勢に戻ります。痛みを感じない範囲で行い、20〜30度伸展できるようにしていきます。

中級
両手を上げ、肘を曲げて手が顔の前に来るようにして立ち、背中を伸ばしたまま股関節から前屈します。初級と同様に90度前屈できるようにしていきます。

最初の姿勢から、手と腕を同じ位置に保ちながら、体幹をゆっくりと後ろに反らしていきます。これも初級と同様に20〜30度伸展できるようにしていきます。

上級
両腕を頭の上に上げ立ち、初級・中級同様に前屈、後屈を行います。


⑥回旋・前屈エクササイズ
立位から、体幹を回旋させ手を逆の腰にタッチします。
最初の姿勢に戻り、もっと大きく体幹を回旋し、手を逆の大腿にタッチします。
最初の姿勢に戻り、もっと大きく体幹を回旋し、手を逆の下腿にタッチします。
最初の姿勢に戻り、もっと大きく体幹を回旋し、手を逆の足首にタッチします。
キャットバック・オールドホース
四つ這いで息を吐きながら背中を丸めるように体幹中央部を引き上げ、5秒静止します。

息を吸いながら体幹中央を床に沈め、腹部はリラックスさせながら頭と臀部を持ち上げ、5秒静止します。

スポンサードサーチ
傍脊柱筋(脊柱起立筋と深層筋)のトリガーポイントと腰痛予防・改善のためのストレッチとトレーニング
傍脊柱筋(脊柱起立筋と深層筋)の部位と機能
脊柱起立筋は、浅層にあり脊柱と並行して走る長い筋群で、頭最長筋、胸腸肋筋、腰腸肋筋などが含まれます。
これらは、最終的に大きな腱の塊に融合し、仙骨に停止します。
脊柱起立筋のうち、脊柱に最も近く位置するのが最長筋で、そこから外側に少し離れた位置にあるのが腸肋筋です。
脊柱起立筋の各筋は、脊柱起立筋群より長さは短く、その多くが肋骨に付着しています。
そのためこの筋群にトリガーポイントが形成され、片方の筋が短縮すると脊柱がその側に引っ張られて、脊柱の位置とアライメントに影響することになります。
深層筋には半棘筋、多裂筋、回旋筋は椎骨から椎骨、椎骨から肋骨、椎骨から腰部、椎骨から仙骨、椎骨から骨盤へと走行しており、脊柱に対して対角線上に位置しており、各椎骨の位置とアライメントに影響します。
傍脊柱筋の協働作用により、脊柱の伸展が行われます。また、左右の筋肉が個別に働くことで、脊柱や体幹の回旋や側屈の補助が行われます。
傍脊柱筋は直立姿勢維持に働き、細かな姿勢のコントロールを行います。咳をした際の呼吸補助の役割もあります。
重力や腹筋群の短縮に対する働きもあり、猫背を防ぐ役割もあります。

出典:誰でもできるトリガーポイントの探し方・治し方 腰痛
傍脊柱筋(脊柱起立筋と深層筋)のトリガーポイントと関連痛
傍脊柱筋(脊柱起立筋と深層筋)にトリガーポイントが形成されると、強い痛みを引き起こすことがあります。
それにより立ち上がれなくなるような場合もあります。
トリガーポイントは脊柱に沿ったどの位置でもできる可能性があります。
胸最長筋では、臀部の上下方へ痛みを送る2つのトリガーポイントがあります。
また、中央部のトリガーポイントでは臀部上方、腹部、肩に関連痛がみられます。
腰腸肋筋のトリガーポイントでは、腰や臀部中央、下方に関連痛がみられます。
多裂筋と回旋筋では、頭部から尾骨や臀部までの付着している脊柱周囲の局所的な痛みを送ります。
多裂筋のトリガーポイントは、尾骨や腹部、臀部、大腿上部にも関連痛がみられます。
このトリガーポイントが悪化すると、起き上がれないほどの痛みや、わずかな体幹回旋運動でも痛みを生じさせます。

出典:誰でもできるトリガーポイントの探し方・治し方 腰痛
傍脊柱筋(脊柱起立筋と深層筋)を痛める原因
・重い荷物の持ち上げ、押す、引っ張るなどの動作
・転倒しそうになって急に姿勢を立て直す動作
・長時間の腰をかがめる動作
・自動車事故などの急な衝撃
・筋疲労があるときのかがむ、ねじる、のばすなどの動作
・不良な座位姿勢
・前傾姿勢
・猫背による傍脊柱筋の負荷
・広背筋、下後鋸筋、腹直筋、腰方形筋、腸腰筋のトリガーポイント
傍脊柱筋(脊柱起立筋と深層筋)のトリガーポイントが疑われる症状
・背部、臀部の痛み
・脊柱の動かしにくさや痛み
・椅子からの立ち上がり困難や痛み
・靴を履くときの動作で関節可動域制限がある(痛みある場合もない場合もある)
・背部筋力低下
・直立姿勢、階段の上り動作が困難
・脊柱の両or片側の深部痛
・車の乗降がしにくい
・動けないほどの背部痛
・椎骨の局所的な痛み
傍脊柱筋(脊柱起立筋と深層筋)の評価
立位での床タッチテスト
裸足で立ち、腹筋はリラックスさせます。膝を曲げずに前屈して指先を床につけていき、痛みがあればそこでストップさせます。この時の床と指先の距離を計測します。
40歳以下で、ハムストリングスに問題がない場合、床に指をつけることができれば合格範囲となります。
40歳以上の人では、年齢が10歳増加する毎に2.5㎝のハンデをつけていきます。ハンデよりも指先と床との距離が開く場合や、背部・臀部・大腿後面・下腿後面に痛みがある場合、傍脊柱筋、大臀筋、ハムストリングス、ヒラメ筋にトリガーポイントがある可能性があります。
このテストでは傍脊柱筋の問題のみをみるテストではないため、テストで陽性の場合、別のテストを行いながら判別していく必要があります。
立位での体幹回旋テスト
深層筋を評価するテストです。
壁を背にして30㎝程度離れ、足は真っ直ぐ前に向けます。そこから左右どちらかに体幹を回旋させます。
このとき、手がつかない場合や脊柱深部に痛みを感じる場合、深層筋にトリガーポイントがある可能性が高いといえます。
傍脊柱筋(脊柱起立筋と深層筋)への治療の考え方
傍脊柱筋の治療前に、腰方形筋や腸腰筋、腹筋の機能低下により姿勢の崩れがないかという視点が必要です。
そこに問題がある場合、まずはそこを治療し、姿勢のバランスを整えてから、傍脊柱筋の治療を行っていきます。
痛みなく筋を良好な状態にするには、体幹前後面の筋に柔軟性と筋力が必要になります。
傍脊柱筋(脊柱起立筋と深層筋)への治療法:圧迫
圧迫を行う場合、不快感がない程度に行うのが重要であり、痛みが強い場合は患部を温める(ホットパック)ことから始めると良いです。
圧迫を加える部位は筋の端から端まで詳しくチェックしていきます。
立位で壁を背にしての圧迫
ストッキッングにテニスボールを入れ、それを肩越しに落とし壁につけ、ゆっくり呼吸をしながらボールに寄りかかり圧をかけていきます。肩甲骨のすぐ下から下方へボールを移動させていきます。下まで行くと2.5㎝程度外側にずらし、同様に下方に降りていきます。
床でローラーを使用しての圧迫
臀部にローラーが当たるようにし、体をゆっくりとローラーの上に動かします。この時脚をつかって体がローラーに当たる部位をコントロールします。
臀部から上方にずらしていきます。この時、片脚を逆脚にかけ(脚を組み)、かけられた側に両脚を倒すことで、脊柱の筋がストレッチされた状態で圧迫することが可能となります。
私は筋膜リリースに適しているランブルローラーを使用しています。


傍脊柱筋(脊柱起立筋と深層筋)への治療法:ストレッチ
椅子座位で床タッチ
椅子座位で床に向かって前屈し、床に手をつけます。この時腹筋はリラックスさせておいて、そこから起き上がって深呼吸し、脊柱起立筋を収縮させます。その後もう一度深く前屈します。
片脚の胸への引き寄せ
仰向けで片脚を同じ側の脇に引き寄せ、膝を胸に押し付けます。この時腹筋はリラックスしたままで、手は大腿後面に置き脚を抱えるようにします。
両脚の胸への引き寄せ
仰向けで両大腿後面を抱えて、両脚を胸に引き寄せます。臀部と尾骨は床から離れるのが理想です。この時腹筋はリラックスさせておきます。
チャイルドポーズ
正座で体幹を大腿に、額を床につき、腕を前に伸ばします。

傍脊柱筋(脊柱起立筋と深層筋)への治療法:コントラクト・リラックス
コントラクト・リラックスは、抵抗を利用した筋収縮と弛緩を交互に繰り返すことで、可動性を高めていくストレッチです。
回旋筋群、多裂筋群
座位で痛みのない範囲でできる限り大きく体幹回旋させ、2呼吸の間静止し、弛緩させ向きを変えて同様にしていきます。回旋の際に、背中を少し反らせることでより効果的なストレッチとなります。
脊柱起立筋群
うつ伏せで両方or片方の手や脚を上げます。
脊柱起立筋のトリガーポイントに関することは、以下の記事も参照してください。
自分でできる腰痛解消法!多裂筋のほぐし方、緩め方!
自分でできる腰痛解消法!腰腸肋筋のほぐし方、緩め方!
自分でできる腰痛解消法!胸最長筋のほぐし方、緩め方!
傍脊柱筋(脊柱起立筋と深層筋)への治療法:トレーニング
キャットバック・オールドホース
四つ這いで息を吐きながら背中を丸めるように体幹中央部を引き上げ、5秒静止します。

息を吸いながら体幹中央を床に沈め、腹部はリラックスさせながら頭と臀部を持ち上げ、5秒静止します。

骨盤前後傾運動
座位で息を吸いながら腹筋をリラックスさせ、腹部をゆっくりと前に突き出しながら骨盤を前傾させます。
息を吐きながらゆっくりと腰を後ろに突き出しながら腹部を引き骨盤を後傾させます。
スーパーマン
初級
うつ伏せで体の前で腕を組み頭を乗せます。片脚をゆっくり持ち上げ5秒静止し、戻します。逆脚も同様に行います。

中級
初級と同じ姿勢から両脚を持ち上げ5秒静止し、ゆっくり元に戻します。

上級
左足、右腕、頭を持ち上げ5秒静止しゆっくり元に戻します。

右足、左腕、頭を持ち上げ5秒静止しゆっくり元に戻します。
両腕、両脚、頭を同時に持ち上げ5秒静止しゆっくり元に戻します。

スレッドザニードル
四つ這いで頭頸部、体幹を右に回旋させ左手は胸の下を通り右に伸ばします。

左腕を抜き、頭頸部、体幹を左に回旋させながら天井に上げます(視線は指先)。

負荷をかける場合は、動かす手に重りを持たせると良いです。
体幹回旋・伸ばし
立位で左脚に体重をかけ、右足を左脚の後ろでクロスさせます。両手もそれに合わせて後ろにスイングします。

右足を前に出し、体幹を右に回旋させて、右手を右後ろ、左手を右上にスイングさせます。

負荷を大きくする場合には、踏み出す幅を大きくし、体幹回旋も大きくすることで難易度が上がります。
他法
前途した「椅子座位での床タッチ」や腸腰筋で紹介した「回旋・前屈エクササイズ」も傍脊柱筋のトレーニングとしては重要です。
スポンサードサーチ
腸腰筋のトリガーポイントと腰痛予防・改善のためのストレッチとトレーニング
腸腰筋とトリガーポイント
腸腰筋は腰筋と腸骨筋からなります。
腰筋は腹腔深部の椎骨前面から起始し、大腿骨の小転子に停止します。
腸骨筋は骨盤の内側全体から起始し、腰筋と合流していきます。
腸腰筋のトリガーポイントは、片方、または両方にできる可能性があります。
腸腰筋の主な作用は、上半身安定の補助(座位・立位の体幹直立位の保持)があります。
また腰筋は走る際に重要な働きをし、年齢とともに筋の密度が低下すると言われています。
他の作用としては、股関節からの前屈、大腿を胸につける時の補助、下肢を閉じたり外旋の補助、下肢固定での上体起こしの補助をします。

出典:誰でもできるトリガーポイントの探し方・治し方 腰痛
腸腰筋のトリガーポイントのパターンは3つあり、これらは脊柱に並行して上下に走る痛みの原因となることがあります。
最上位のトリガーポイントは臍から約5㎝外側にあります。
真ん中のトリガーポイントは腸骨の内側で、腸骨稜から約2.5㎝下がった位置にあります。
最下位のトリガーポイントは大腿上にあります。
脊柱と並行して上下に走る痛みがあればまず腸腰筋のトリガーポイントを疑う必要があります。
また、両側の腸腰筋が収縮している時には、腰部を横に走る痛みを感じる場合もあります。
腸骨筋は大腿筋皮神経を絞扼することがあり、大腿前面・側面の灼熱感やしびれの原因となることがあります。

出典:誰でもできるトリガーポイントの探し方・治し方 腰痛
腸腰筋を悪化させる原因とトリガーポイントが疑われる症状
腸腰筋を悪化させる要因
①長時間の座位
②急な姿勢の変換
③長時間の運転、膝が臀部より高くくるような低い椅子に長時間座る
④体を丸めて寝る、腹臥位で寝ることによる腸腰筋の短縮
⑤腰椎の手術
⑥脊柱側弯症
⑦長時間の前屈姿勢
⑧腹部の慢性的な緊張
トリガーポイントの疑い
①脊柱と並行に上下に走る痛み
②立位で股関節で前屈している、あるいは左右どちらかにひねった状態で前屈しがち
③座位姿勢からまっすぐ立ち上がれない
④背中を伸ばして立つと背中に痛みがある
⑤低い椅子から立ち上がるのが難しい
⑥痛みがひどく、手や膝をついて這って移動する必要がある
腸腰筋のトリガーポイントを見つける方法(評価)
座位で胸を大腿につける
腸腰筋が正常に短縮するかを評価する方法です。
背もたれがまっすぐな椅子に腰掛け、前屈して胸を大腿につけていきます。痛みがなく前屈できれば腸腰筋の機能は正常です。
胸がつかない、もしくは腰に痛みがある場合、腸腰筋あるいは伸びている背部の筋にトリガーポイントが疑われます。
肥満で腹部が出ている方では深い前屈ができませんが、その際は腸腰筋(腹部)が硬くなっていないか、腰痛が生じないかを判断基準にすると良いでしょう。
足上げホールドテスト
背臥位で骨盤を床に押し付けます(腰が床から浮かないように)。膝を伸ばしたまま、床から30㎝程上げていき、そのまま10秒静止します。
この時、腰痛や筋の痙攣がなく、腰を床につけたまま10秒間足を上げ続けていられれば、腸腰筋に問題はなく、良姿勢保持のための最低限の筋力があると考えます。
腰が浮く、痛みがある、10秒静止困難な場合、腸腰筋のトリガーポイントがある可能性が高いといえます。
*椎間板ヘルニアの診断を受けている方には行ってはいけません。

腸腰筋のストレッチ
①座位での腸腰筋ストレッチ
椅子に腰掛け、体を片方にずらし、ずらした側の下肢を後ろに伸ばします。上半身は真っ直ぐに保持しておきます。
下肢をできるだけ伸ばし、下に下げていくとより効果的です。各足最低3回ずつ、1分程度かけてストレッチを行います。

②立位での腸腰筋ストレッチ
台や椅子の背もたれをつかみ、上半身をまっすぐたもったまま、片方の下肢を後ろに伸ばしていきます。体を少しずつ後ろに反らしていくとより効果的です。各足最低3回ずつ、1分程度かけてストレッチを行います。

③うつ伏せで行う腸腰筋ストレッチ
うつ伏せで大腿の下に厚いクッションを置き、骨盤と腹部はリラックスを保ちながらストレッチしていきます。各足最低3回ずつ、1分程度かけてストレッチを行います。柔軟性に応じて、クッションの高さを変えていきます。
④ドアを利用した腸腰筋ストレッチ
腕を上げ、両側の側柱に手をかけます。下肢を前後に開いて、上体を後ろにそらしながらゆっくりと前方に体重をかけていきます。各足最低3回ずつ、1分程度かけてストレッチを行います。

コントラクト・リラックス
コントラクト・リラックスは、抵抗を利用した筋収縮と弛緩を交互に繰り返すことで、可動性を高めていくストレッチです。前途のストレチの合間に行うことで、さらに効果を高めることができます。
①椅子座位での腸腰筋コントラクト・リラックス
大腿を上げると同時に手で押し戻します(筋収縮)。そのまま10秒静止してから、息を吐いて筋を弛緩させます。各足3回ずつ行います。

②立位での腸腰筋コントラクト・リラックス
台や椅子の背をつかんで立ち、片方の下肢を後ろに伸ばし、床から30㎝程度上げます。10秒静止してから息を吐き筋を弛緩させ、前途の腸腰筋ストレッチ②を行います。各足3回ずつ行います。
*これは、臀筋や脊柱起立筋などの拮抗筋を収縮させることによる腸腰筋のリリース方法です。

③仰向けでの腸腰筋コントラクト・リラックス
仰向けで片方の膝を胸に引きつけ、手で大腿後面を抱えます。大腿に手が届かない場合、タオルを利用します。
大腿を引き離すように力を入れながら、10秒静止します。息を吐き、腹部を弛緩させできるでけ胸に引きつけます。各足3回ずつ行います。
応用として、膝を反対側の肩に向かって引きつける方法があります。
腸腰筋のトレーニング
腸腰筋にトリガーポイントがあると痛みとともに筋力低下を引き起こします。このとき、トリガーポイントの処置をせずに筋力トレーニングをしても効果は上がりにくくなります。そのため、まずはトリガーポイントを正常化し、関節可動域の獲得が必要になります。
①大股歩き
通常歩幅での歩行、大きな歩幅での歩行を交互に行います。
②ヒップツイスト
両足の先を外に向け、右足を左足の前に出します。


右足先を軸に右股関節を内旋させます。

ゆっくりと元の姿勢に戻します。
機能レベルに合わせて、スピードや繰り返しの回数を設定していきます。
③足先の内/外エクササイズ
立位で足先を内に向け静止し、次に足先を外側に向けます。


少しずつ内/外に向ける角度を大きくしていきます。
④四つ這いでのトレーニング
四つ這いで下肢を胸に引きつけ、
・下肢を後方に高く振り上げます。

・下肢を胸を横切り逆の肘へ引きつけます。

・膝を曲げたまま外側に向け、股関節の高さまで引き上げます。

・最初の姿勢に戻します。
⑤体幹屈曲、伸展を伴うエクササイズ
初級
膝を伸ばして立ち、両手を後ろ回します。背中を伸ばしながら股関節から屈曲し、ゆっくりと最初の姿勢に戻ります。痛みを感じない範囲で行い、90度前屈できるようになるまで行います。

最初の姿勢から、両手を腰に当て、体幹をゆっくりと後ろに反らしていきます。ゆっくりと元の姿勢に戻ります。痛みを感じない範囲で行い、20〜30度伸展できるようにしていきます。

中級
両手を上げ、肘を曲げて手が顔の前に来るようにして立ち、背中を伸ばしたまま股関節から前屈します。初級と同様に90度前屈できるようにしていきます。

最初の姿勢から、手と腕を同じ位置に保ちながら、体幹をゆっくりと後ろに反らしていきます。これも初級と同様に20〜30度伸展できるようにしていきます。

上級
両腕を頭の上に上げ立ち、初級・中級同様に前屈、後屈を行います。


⑥回旋・前屈エクササイズ
立位から、体幹を回旋させ手を逆の腰にタッチします。
最初の姿勢に戻り、もっと大きく体幹を回旋し、手を逆の大腿にタッチします。
最初の姿勢に戻り、もっと大きく体幹を回旋し、手を逆の下腿にタッチします。
最初の姿勢に戻り、もっと大きく体幹を回旋し、手を逆の足首にタッチします。
腸腰筋のトリガーポイント解消のためにできること
長時間の運転では適度に休憩し、立位をとりストレッチを行うようにします。
睡眠時に丸まって寝る癖がある方は、姿勢を変えてみるようにします。
腹部〜大腿部の付け根を温めようにします。
椅子座位では座面に傾斜をつけ、大腿が膝より下にくるようにします。
マットレスの硬さに注意します。
スポンサードサーチ
腰方形筋のトリガーポイントと腰痛予防・改善のためのストレッチとトレーニング
腰方形筋とその機能
腰方形筋は第12肋骨、腰椎の横突起、腸骨稜の一部に付着している、腹腔後壁を形作る筋です。
腰方形筋は咳や息を力強く吐く際の補助をし、片側のみで働くときは、体幹の側屈や収縮側の骨盤を引き上げる作用があります。
座位や立位では両側の腰方形筋の収縮により体幹を伸展させ、腰椎の安定性に関わっています。

出典:誰でもできるトリガーポイントの探し方・治し方 腰痛
腰方形筋とトリガーポイント
腰方形筋のトリガーポイントは、主に浅層と深層の2つがあります。
浅層のトリガーポイントは臀部外上・下方、臀部中央、右下腹部周辺に関連痛を送ります。
深層のトリガーポイントは脊椎付近にあり、臀部下方や中央の仙腸関節上に関連痛を送ります。
腰方形筋が常に収縮している状態だと、強い痛みや側臥位をとることが困難になります。
腰方形筋のトリガーポイントは、傍脊柱筋、腸腰筋、腹斜筋、広背筋のトリガーポイントを活性化させる要因とります。
また中・小臀筋も活性化され、座骨神経痛に似た症状を引き起こすこともあります。

出典:誰でもできるトリガーポイントの探し方・治し方 腰痛
腰方形筋を悪化させる原因
腰方形筋が慢性的に緊張(収縮)していると、骨盤が前or後傾された状態で固定され、腰方形筋のトリガーポイントを活性化させてしまいます。
骨盤の左右差や脚長差、体幹と比較し上腕が短いといった身体構造上のアンバランスは、腰方形筋のトリガーポイントの原因となりえます。
座位姿勢や椅子の環境、睡眠時の姿勢にも影響を受けます。
椅子が合っていないことにより体が片側に傾く姿勢をとっていることや、睡眠時に右側を下にして寝ていると、右の腰方形筋は伸張し、左の腰方形筋は短縮します。
腰方形筋は腰椎の横突起に付着しており、一方の筋が短縮すると、その側の脊椎が引っ張られて傾き、椎間が狭くなります。これがひどくなると神経根を圧迫します。
坐骨神経は腰方形筋が慢性的に緊張が高いと神経根性の座骨神経痛が生じます。
また、椎間板の圧迫から椎間板突出を招くこともあります。
腰方形筋のトリガーポイントが疑われる症状
・痛みで寝返りがうてない
・立位、歩行時の痛み
・体幹前屈、側屈がしにくい
・咳やくしゃみで痛みがある
・姿勢のバランスが崩れている
・静止時の深部痛
・腰を少し動かしただけでも痛い
・激しい痛みや痙攣により四つ這い移動しかできない
姿勢のバランスに関して骨盤の左右差チェックと、骨盤矯正の方法については下記の記事を参照してください。
腰方形筋のテスト
足を肩幅に開き立ち、手のひらは大腿外側につけます。
指が大腿外側に沿いながら膝の外側まで届くように体幹を側屈させ、元の姿勢に戻します。

次にチェックポイントを通して確認を再度行います。
・中指の先が膝より下に届くまで側屈できない
・腰や股関節に痛みがある
・立位や歩行中に手を腰に当てて押すと痛みが軽減する
・腰を左右に振る動作が難しいor痛みがある
・骨盤の前後傾、片側の骨盤挙上が困難or腰や臀部に痛みが生じる
これらに当てはまることがあれば腰方形筋のトリガーポイントが活性化されている可能性が高いといえます。
腰方形筋の治療:圧迫
痛みが強い場合、はじめは手で軽くマッサージしたり、筋を温めることで筋緊張の緩和を図ります。また、腰方形筋上の皮膚をつまみ上げ、組織間のリリースする方法もあります。痛みが軽減してから圧迫に移るようにします。
側臥位でのローラーを使用した圧迫
側臥位で肘か腕で体を支え、その下にローラーを入れます。腕で体重の掛け方をコントロールします。

圧迫用ローラー
私は筋膜リリースに適しているランブルローラーを使用しています。

腰方形筋の治療:ストレッチ
立位
足を30㎝程離して立ち、片方の腕を頭上に伸ばし、体幹を側屈させていきます。逆の手で補助するとさらにストレッチが可能になります。
これにより、側腹部の筋の遠心性収縮も促されるため、骨盤の左右差が矯正させる働きもあります。左右それぞれ3回行います。

側臥位
側臥位でクッションをウエストの下に置きます。腕は頭の方に挙げ、下側の足は曲げ、上側の足は伸ばしてリラックスさせます。ストレッチ後、上側の骨盤を挙上し、ストレッチした側の脇腹を10秒ほど収縮させ、弛緩することでさらに効果が高まります。
痛み具合に応じて枕の高さを調節していきます。
フィットネスボール(バランスボール)を使用したストレッチ
バランスボール(固定用のリングがあればなお良し)の隣にしゃがみこみ、壁側の足を伸ばして壁で支えて、臀部側面をボールに押し付けます。
下側の手で支えてボールの上に体側を乗せ、上側の手を頭上に伸ばし足を少し開きます。
コントラクト・リラックス
コントラクトリラックスは、抵抗を利用した動作(収縮)と弛緩を交互に行うことで、可動性を高めていく方法です。
ストレッチと交互に行うことでより効果的に可動性を改善することができます。
足を肩幅に開き立ち、一方の手を同側の腰に当て、股関節を押します。それに抗して股関節(骨盤)を引き上げます。10〜15秒静止してから弛緩し、左右3回行います。
腰方形筋の治療:トレーニング
ヒップスイング
立位で臀部を左右にスイングさせます。この時、肩・胸部は動かないように注意します。


ヒップ挙上
立位で左右の骨盤を10回ずつ上げて下ろします。

背中ひねり
椅子に座り、股関節と下腿は正面に向けたまま、息を吐きながら痛みを感じない程度に上体を回旋させます。

ツイスト
立位で腕は脇につけておきます。
右足を後ろに引き、両腕を左にスイングさせます。
逆も行いますが、その都度腕の高さを変えると効果的です。

スポンサードサーチ
ハムストリングのトリガーポイントと腰痛予防・改善のためのストレッチとトレーニング
ハムストリングとその機能
ハムストリングは、半膜様筋、半腱様筋、大腿二頭筋の総称です。
大腿二頭筋は長頭、短頭とありますが、短頭はハムストリングには含みません。
3つの筋は坐骨結節から始まり、内側は脛骨、外側は腓骨に付着します。
ハムストリングが収縮すると、股関節伸展や膝屈曲に作用します。
また、骨盤底を安定の補助を行います。
半腱様筋と半膜様筋は大腿を内旋させ、大腿二頭筋は大腿を外旋させます。
ハムストリングとトリガーポイント
ハムストリングのトリガーポイントは、殿部下部に向かって関連痛を送る事が多いです。
また大腿、膝、ふくらはぎの後面に関連痛を送る事もあり、坐骨神経痛と誤解されやすくなっています。
慢性的なハムストリングの緊張は、骨盤を後方に傾け、腱が骨に付着する部分に痛みを引き起こします。
付着部が腱炎となり、トリガーポイントが形成され、硬貨状態が続くと、骨棘や石灰化を引き起こします。

出展:だれでもできるトリガーポイントの探し方・治し方(腰痛)
ハムストリングのトリガーポイントを悪化させる要因
・長時間の座位で、椅子の前縁がハムストリングを圧迫する
・長時間の座位により、ハムストリングがそれに適応しようと常に短縮する
・長時間の膝を曲げた姿勢
・長時間のベッド休養(安静)
・足を組んで座る
・膝を伸ばしたまま重いものを持ち上げる
・自動車事故
・過剰な筋力トレーニング
ハムストリングのトリガーポイントが疑われる症状
・大腿後面の痛み
・痛む箇所を圧迫すると、殿部、大腿後面、膝、ふくらはぎに痛みが走る
・坐骨神経痛様の痛み
・突然膝の力が抜ける
・跛行
・座位や歩行時の痛み
・椅子から立ち上がる、組んでいる足を戻した時の傷み
・速く歩こうとすると体が前かがみになる
・坂道を歩く、走る、ジャンプが難しくなる
ハムストリングの治療:圧迫
痛みが強い場合、はじめは手で軽くマッサージしたり、筋を温めることで筋緊張の緩和を図ります。また筋上の皮膚をつまみ上げ、組織間のリリースする方法もあります。痛みが軽減してから圧迫に移るようにします。
仰向けでのローラーを使用した圧迫
仰向けで肘か腕で体を支え、その下にローラーを入れます。腕で体重の掛け方をコントロールします。
痛みが強い場合、ローラーの上にタオルを覆うなどして調整します。


圧迫用ローラー
私は筋膜リリースに適しているランブルローラーを使用しています。

ハムストリングの治療:ストレッチ
壁を背にして座り、ストレッチ
壁を背にして座り、はじめのうちは片方の足を曲げ、もう片方を伸ばして行います。
背中と頭を壁に押し付け、背中をまっすぐにしたまま股関節を曲げて体幹を前屈させます。
*背中が丸まっていると背中のストレッチになってしまうため注意が必要です。

壁を背にして、足を開いてストレッチ
殿部に痛みを送る部位に特化したストレッチです。
壁を背にして背筋を伸ばして座り、足を60度程度開きます。
股関節から体幹を曲げ、そこから足先に向かい手を伸ばします。
次に足の間に向かって同様に前屈します。

タオルを利用したストレッチ
仰向けになり、タオルを足の裏にかけ、膝関節はできるだけ伸ばしながら、足を胸に近づけていきます。

ハムストリングのトレーニング
体幹屈曲、伸展を伴うエクササイズ
初級
膝を伸ばして立ち、両手を後ろ回します。背中を伸ばしながら股関節から屈曲し、ゆっくりと最初の姿勢に戻ります。痛みを感じない範囲で行い、90度前屈できるようになるまで行います。

最初の姿勢から、両手を腰に当て、体幹をゆっくりと後ろに反らしていきます。ゆっくりと元の姿勢に戻ります。痛みを感じない範囲で行い、20〜30度伸展できるようにしていきます。

中級
両手を上げ、肘を曲げて手が顔の前に来るようにして立ち、背中を伸ばしたまま股関節から前屈します。初級と同様に90度前屈できるようにしていきます。

最初の姿勢から、手と腕を同じ位置に保ちながら、体幹をゆっくりと後ろに反らしていきます。これも初級と同様に20〜30度伸展できるようにしていきます。

上級
両腕を頭の上に上げ立ち、初級・中級同様に前屈、後屈を行います。


四つ這いでのトレーニング
四つ這いで下肢を胸に引きつけ、
・下肢を後方に高く振り上げます。

・下肢を胸を横切り逆の肘へ引きつけます。

・膝を曲げたまま外側に向け、股関節の高さまで引き上げます。

・最初の姿勢に戻します。
足を内側/外側に向けての坂道登り
坂道を登るときに、足先を内側に向けてしばらく歩き、次に足先を外側に向けてしばらく歩きます。
これにより、ハムストリンング、殿筋、ヒラメ筋の可動域を改善させるのに有効です。
スポンサードサーチ
梨状筋のトリガーポイントと腰痛予防・改善のためのストレッチとトレーニング
梨状筋とその機能
梨状筋は大殿筋と中殿筋の下で、殿部上方の深くに位置しています。
内側は仙骨に付着し、外側は大腿骨に付着しています。
梨状筋は、足をまっすぐ、もしくは後方に伸ばした状態での外旋に作用します。
股関節を安定させるために大腿骨頭を寛骨臼内に維持する作用があります。
立位では体重負荷を伴う運動で、大腿が急に内旋することを防ぎます。

出典:誰でもできるトリガーポイントの探し方・治し方(腰痛)
梨状筋とトリガーポイント
梨状筋の内側や中央のトリガーポイントは、仙骨周辺や殿部全体、大腿後面に関連痛を送ります。
慢性的な梨状筋の緊張は、座骨神経などの神経絞扼につながり、腰や鼠蹊部、殿部、股関節、足の痛みや痺れ、排便時の直腸の鋭い痛みなどの症状を引き起こす可能性があります。

出典:誰でもできるトリガーポイントの探し方・治し方(腰痛)
梨状筋のトリガーポイントを悪化させる要因
・重いものの持ち上げや下ろしなどの急な負荷
・転倒、転びそうになる、自動車事故などの急な過負荷
・長距離走
・長時間の運転
・足を組んでの長時間の座位
・つま先を外側に向けて歩く
梨状筋のトリガーポイントが疑われる症状
・歩行時の痛みがある、片方の足を引きずる、跛行がある
・座った時に落ち着かず、体重を左右に移動させる傾向がある
梨状筋のトリガーポイントのテスト
足を内側/外側に向ける
自然に立ったり歩いている時に、自分の足のつま先が外側に向いているならば、中殿筋や小殿筋、梨状筋に緊張や短縮がある可能性が高くなります。
足を内側に向ける(股関節内旋)、足を外側に向ける(股関節外旋)ときに痛みがあれば、中殿筋や小殿筋、梨状筋のトリガーポイントを疑います。
ボンネットテスト
仰向けで右足は伸ばし、左足を右側のふくらはぎの横にクロスさせて、かかとを床につけます。
左足を右膝の上までスライドさせることができなければ、左の中殿筋や小殿筋、梨状筋にトリガーポイントがある可能性が高くなります。

膝クロステスト
背を伸ばして椅子に座り、左足を右足の上にクロスさせます。
右膝の上に左足の足首かふくらはぎの一部までしかクロスできない場合、小殿筋と梨状筋にトリガーポイントがある可能性が高くなります。

外転抵抗テスト(梨状筋のトリガーポイントに関する最も確実なテスト)
椅子に座り、パートナーに両膝の外側に手を当ててもらいます。
パートナーはそのまま押さえながら、膝を外に開いてパートナーの手を押します。
痛みを感じる、または左右どちらも押すことができないのであれば、梨状筋、中殿筋、小殿筋にトリガーポイントがある可能性が高くなります。
梨状筋の治療:圧迫
痛みが強い場合、はじめは手で軽くマッサージしたり、筋を温めることで筋緊張の緩和を図ります。
また筋上の皮膚をつまみ上げ、組織間のリリースする方法もあります。痛みが軽減してから圧迫に移るようにします。
仰向けでのローラーを使用した圧迫
仰向けでで肘か腕で体を支え、その下にローラーを入れます。腕で体重の掛け方をコントロールします。
痛みが強い場合、ローラーの上にタオルを覆うなどして調整します。
片方の足をクロスさせ、その足をできるだけ胸に近づけます。

圧迫用ローラー
私は筋膜リリースに適しているランブルローラーを使用しています。

梨状筋の治療:ストレッチ
足をクロスさせるストレッチ
仰向けで足をクロスさせ、膝になるべく近い位置につけます。
足首またはかかとを掴み、殿部と足は床につけたまま、足を股関節の方向へ引き寄せます。

膝をクロスさせてストレッチ
仰向けで足をクロスさせ、手で大腿と膝を引き上げ、下側に倒します。

足を横に倒してのストレッチ
仰向けで片方の足をもう一方の膝上にクロスさせ、両足をクロスした足側に倒します。

床に座り片方の膝を抱える
床に座り、足をクロスさせて膝を抱え、胸に引き寄せます。
そこから、膝を抱える腕の力とは逆方向に膝に力を加えて殿筋を収縮させます。
15秒経てば力を抜き、次にさらに胸との距離が近くなるように膝を引き寄せます。

足をクロスさせてストレッチ
椅子に座り、足をクロスさせ、両大腿がもたれ合うようにします。

座って4の字ストレッチ
椅子に座り足をクロスさせ、大腿部に足首がくるようにします。
膝を地面と水平まで持ってこられるようにします。

次に、大腿を抱えて胸に引き寄せます。

座って床にタッチ
椅子に座り、足をクロスさせて、前屈して床にタッチします。

梨状筋の治療:トレーニング
足先の内/外エクササイズ
立位で足先を内に向け静止し、次に足先を外側に向けます。


少しずつ内/外に向ける角度を大きくしていきます。
足のスイングエクササイズ
椅子の背を持ちながら、以下の動作を行います。
①前にスイング

②後ろにスイング

③外側にスイング

④内側にスイング(前側を通って)

⑤内側にスイング(後ろ側を通って)

四つ這いでのトレーニング
四つ這いで下肢を胸に引きつけ、
・下肢を後方に高く振り上げます。

・下肢を胸を横切り逆の肘へ引きつけます。

・膝を曲げたまま外側に向け、股関節の高さまで引き上げます。

・最初の姿勢に戻します。
スポンサードサーチ
中殿筋、小殿筋のトリガーポイントと腰痛予防・改善のためのストレッチとトレーニング
中殿筋、小殿筋とその機能
中殿筋の後部は大殿筋に覆われ、小殿筋は中殿筋に覆われています。
中殿筋、小殿筋は、歩行や走行、片足立位の際に骨盤の安定に作用し、また大腿部を胸の方向に引き上げる補助も行います。
中殿筋の前面に向かう筋肉は股関節内旋に働き、後部の繊維は股関節外転に作用します。
小殿筋は主に股関節外転に作用し、前面の筋は股関節内旋、後面の筋は股関節外旋に作用します。

出典:誰でもできるトリガーポイントの探し方・治し方(腰痛)
中殿筋、小殿筋とトリガーポイント
中殿筋のトリガーポイントは、殿部や大腿上部に関連痛を送ります。

出典:誰でもできるトリガーポイントの探し方・治し方(腰痛)
小殿筋には明確なトリガーポイントが2つあります。
1つ目は筋の前部で、殿部から下向きの大腿外側から膝、ふくらはぎ、足首にかけて関連痛を送ります。
2つ目は筋後部で、殿部側面や殿部下方、大腿後面、ふくらはぎ後面に関連痛を送ります。

出典:誰でもできるトリガーポイントの探し方・治し方(腰痛)
小殿筋のトリガーポイントは、坐骨神経痛様の症状を引き起こすことがあります。
中殿筋、小殿筋にトリガーポイントが形成される要因
・長時間の運転で右足が同じ位置に固定される
・脚長差があり、それを補おうと一方の殿筋が短くなる
・仙腸関節の問題
・長時間の立位や、体重を片足にかけての立位、左右の脚をくっつけての立位
・体を丸めて寝る姿勢。上になる脚が支えられていない状態で寝る姿勢
・仰向けで重い布団をかけ、脚を広げた状態で寝る姿勢
・スポーツで殿筋を酷使する
・殿部への注射
中殿筋、小殿筋のトリガーポイントが疑われる症状
・脚を横方向に持ち上げるのが困難(股関節外転)
・片足で立つことが難しい
・歩行中に股関節の弱さを感じる
中殿筋や小殿筋のトリガーポイントによる痛みは、激しく、なかなか取れにくく、痛みが和らぐ姿勢を見つけることが難しいことが特徴です。
中殿筋、小殿筋のトリガーポイントを見つける検査
以下に紹介する検査は、中殿筋や小殿筋のトリガーポイントを単独で見つける検査ではありません。多くは梨状筋も調べるものとなっています。
殿筋の治療では、殿筋群として一緒に治療することが可能です。
足を内側/外側に向ける
自然に立ったり歩いている時に、自分の足のつま先が外側に向いているならば、中殿筋や小殿筋、梨状筋に緊張や短縮がある可能性が高くなります。
足を内側に向ける(股関節内旋)、足を外側に向ける(股関節外旋)ときに痛みがあれば、中殿筋や小殿筋、梨状筋のトリガーポイントを疑います。
ボンネットテスト
仰向けで右足は伸ばし、左足を右側のふくらはぎの横にクロスさせて、かかとを床につけます。
左足を右膝の上までスライドさせることができなければ、左の中殿筋や小殿筋、梨状筋にトリガーポイントがある可能性が高くなります。

立位で横に足をスイング
椅子の背に手をかえて支えとし、片足を外側にスイングさせます。
痛みがある、動作が行いにくい、動きが一定でない/ぎこちないなどが見られると、中殿筋や小殿筋にトリガーポイントがある可能性が高くなります。
膝クロステスト
背を伸ばして椅子に座り、左足を右足の上にクロスさせます。
右膝の上に左足の足首かふくらはぎの一部までしかクロスできない場合、小殿筋と梨状筋にトリガーポイントがある可能性が高くなります。

中殿筋、小殿筋の治療:圧迫
痛みが強い場合、はじめは手で軽くマッサージしたり、筋を温めることで筋緊張の緩和を図ります。また筋上の皮膚をつまみ上げ、組織間のリリースする方法もあります。痛みが軽減してから圧迫に移るようにします。
仰向けでのローラーを使用した圧迫
仰向けでで肘か腕で体を支え、その下にローラーを入れます。腕で体重の掛け方をコントロールします。
痛みが強い場合、ローラーの上にタオルを覆うなどして調整します。
片方の足をクロスさせ、その足をできるだけ胸に近づけます。

圧迫用ローラー
私は筋膜リリースに適しているランブルローラーを使用しています。

中殿筋、小殿筋の治療:ストレッチ
足を横に倒してのストレッチ
仰向けで片方の足をもう一方の膝上にクロスさせ、両足をクロスした足側に倒します。

床に座り片方の膝を抱える
床に座り、足をクロスさせて膝を抱え、胸に引き寄せます。
そこから、膝を抱える腕の力とは逆方向に膝に力を加えて殿筋を収縮させます。
15秒経てば力を抜き、次にさらに胸との距離が近くなるように膝を引き寄せます。

足をクロスさせてストレッチ
椅子に座り、足をクロスさせ、両大腿がもたれ合うようにします。

座って4の字ストレッチ
椅子に座り足をクロスさせ、大腿部に足首がくるようにします。
膝を地面と水平まで持ってこられるようにします。

次に、大腿を抱えて胸に引き寄せます。

座って床にタッチ
椅子に座り、足をクロスさせて、前屈して床にタッチします。

立って足をクロス
左足で立ち、右足を後ろでクロスさせます。
体を左に傾けて、右の股関節を右側に押し出します(右股関節周辺の筋のストレッチ)。

中殿筋、小殿筋の治療:トレーニング
足先の内/外エクササイズ
立位で足先を内に向け静止し、次に足先を外側に向けます。


少しずつ内/外に向ける角度を大きくしていきます。
足のスイングエクササイズ
椅子の背を持ちながら、以下の動作を行います。
①前にスイング

②後ろにスイング

③外側にスイング

④内側にスイング(前側を通って)

⑤内側にスイング(後ろ側を通って)

四つ這いでのトレーニング
四つ這いで下肢を胸に引きつけ、
・下肢を後方に高く振り上げます。

・下肢を胸を横切り逆の肘へ引きつけます。

・膝を曲げたまま外側に向け、股関節の高さまで引き上げます。

・最初の姿勢に戻します。
スーパーマン
初級
うつ伏せで体の前で腕を組み頭を乗せます。片脚をゆっくり持ち上げ5秒静止し、戻します。逆脚も同様に行います。

中級
初級と同じ姿勢から両脚を持ち上げ5秒静止し、ゆっくり元に戻します。

上級
左足、右腕、頭を持ち上げ5秒静止しゆっくり元に戻します。

右足、左腕、頭を持ち上げ5秒静止しゆっくり元に戻します。
両腕、両脚、頭を同時に持ち上げ5秒静止しゆっくり元に戻します。

グレープバイン
①自然に立ちます。
②左足を右の後方にずらし、体重を左足にかけます。
右足を右側に一歩だし①の姿勢に戻ります。

③左足を体の前を通り右に出し、体重を左足にかけます。
右足を右側に一歩だし、元の姿勢にもどります。

この動きを前後交互に行いながら一方の方向に進みます。
次に体の向きをかえて同じ手順で行います。
慣れてきたら歩幅を大きくします。
スポンサードサーチ
大殿筋のトリガーポイントと腰痛予防・改善のためのストレッチとトレーニング
大殿筋とその機能
大殿筋は殿部で最も大きい筋肉です。
尾骨、仙骨、腸骨稜にかけて存在し、中臀筋を覆う筋膜とつながっています。
大殿筋は、歩行や立位で体幹を安定させるのに重要な働きをします。
大殿筋とトリガーポイント
大殿筋は、慢性的に筋肉が伸びていることで状態が悪化します。
長時間座っている姿勢がその代表です。
大殿筋は関節が動くすべての範囲において動かすことで、健康な状態に保つことができます。
大殿筋のトリガーポイントは、3つあります。

出典:誰でもできるトリガーポイントの探し方・治し方(腰痛)
1つ目は上方、仙骨周辺です。
2つ目は下部中央、坐骨結節の後方です。
この部位にトリガーポイントがあると、仙骨内とその周辺、殿部上方全体に痛みが生じます。
坐骨付近のために、この部位に体重をかけて座るとひどい関連痛が生じます。
ドーナツ型のクッションは、この痛みの軽減に役立ちます。
3つ目は尾骨周辺に大きな不快感を生じさせます。
大殿筋のトリガーポイントは片側に見つかることが多いですが、これは体重が片側に偏っている人が多いためです。
大殿筋を悪化させる要因
・前かがみになりながら坂道を登る
・後ろに傾きながらの長時間の座位
・滑ったり転倒するなどの急激な負荷
・しりもち
・横向きで膝を曲げながら寝る
・仰向けで足と背中を伸ばしたまま寝る
・殿部への注射
・かがんでから体を起こす動作を頻繁に行う
・立位でうつむくのが習慣化している
・クロールのバタ足
大殿筋のトリガーポイントが疑われる症状
・座ったときの殿部の不快感や痛み
・殿部の深く、尾骨内と周辺部の痛み
・坂道や階段を上るのが難しい
・長時間座ると圧痛や関連痛を感じる
・自分に合う椅子がみつからない
・仰向けで膝を胸に引き寄せるのが難しい
・クロールでバタ足が難しい
・膝を曲げずに体を少し後ろに倒した時に殿部に痛みがある
・つま先を外に向けて歩くことが多い
大殿筋のトリガーポイントのテスト
膝を胸に引き寄せる
仰向けで片方の足を胸に引き寄せます。このとき、反対側の脇へ引き寄せるようにします。
膝がへその上あたりまでしか行かないのであれば、トリガーポイントがある可能性が高くなります。
反対側の胸に引き寄せるときに殿部に痛みがあれば、ほぼ間違いなくトリガーポイントが存在します。
このテストは、ハムストリングスや腸腰筋の短縮を調べる検査でもあります。

椅子に腰掛け足先にタッチ
椅子座位をとり、足先に向かい前屈します。手を床につけられない場合、大殿筋にトリガーポイントがある可能性が高くなります。
床に座り足先にタッチ
床に座り、片方の足を伸ばし、逆足を曲げて少し外側に倒します。
太ももの裏が床から離れないようにしながら、手を伸ばした足先に向けてタッチします。
40歳以下であれば、足先に届かなければ大殿筋にトリガーポイントがある可能性が高いです。
40歳以上であれば、10歳ごとに2.5cm分ハンディキャップをつけます。
このテストでは、傍脊柱筋やハムストリングスの検査でもあります。

【スポンサーリンク】
大殿筋の治療:圧迫
痛みが強い場合、はじめは手で軽くマッサージしたり、筋を温めることで筋緊張の緩和を図ります。また筋上の皮膚をつまみ上げ、組織間のリリースする方法もあります。痛みが軽減してから圧迫に移るようにします。
仰向けでのローラーを使用した圧迫
仰向けでで肘か腕で体を支え、その下にローラーを入れます。腕で体重の掛け方をコントロールします。
痛みが強い場合、ローラーの上にタオルを覆うなどして調整します。



圧迫用ローラー
私は筋膜リリースに適しているランブルローラーを使用しています。

大殿筋の治療:ストレッチ
片方の膝を脇に寄せる
仰向けで片足を逆側の脇に引き寄せます。
それ以上引き寄せれない所まで来たらゆっくり2回深呼吸します。
次に、腕は胸の方に引き寄せたまま、足を戻すように15秒程押します。
これにより、大殿筋がリラックスします。
両膝を胸に引き寄せる
仰向けで、腹筋の力は抜いたまま両膝を胸に近づけます。
床に座り片方の膝を抱える
床に座り、足をクロスさせて膝を抱え、胸に引き寄せます。
そこから、膝を抱える腕の力とは逆方向に膝に力を加えて殿筋を収縮させます。
15秒経てば力を抜き、次にさらに胸との距離が近くなるように膝を引き寄せます。

床に座り片方の足先にタッチ
検査で行ったように、床に座り、片方の足を伸ばし、逆足を曲げて少し外側に倒します。
太ももの裏が床から離れないようにしながら、手を伸ばした足先に向けてタッチします。
殿筋を収縮させるには、手で足首かふくらはぎをつかみ、体幹を起こそうとします。これを20秒程度行います。

床に座り、両足の先にタッチ
床に座り、前屈して両足の先を目指してタッチします。
殿筋の収縮を加えるには、足をつかみ、かかとを床に押し付け、30%の力で背中を伸ばします。これを15秒間行います。
大殿筋の治療:トレーニング
足先の内/外エクササイズ
立位で足先を内に向け静止し、次に足先を外側に向けます。


少しずつ内/外に向ける角度を大きくしていきます。
足のスイングエクササイズ
椅子の背を持ちながら、以下の動作を行います。
①前にスイング

②後ろにスイング

③外側にスイング

④内側にスイング(前側を通って)

⑤内側にスイング(後ろ側を通って)

四つ這いでのトレーニング
四つ這いで下肢を胸に引きつけ、
・下肢を後方に高く振り上げます。

・下肢を胸を横切り逆の肘へ引きつけます。

・膝を曲げたまま外側に向け、股関節の高さまで引き上げます。

・最初の姿勢に戻します。
スーパーマン
初級
うつ伏せで体の前で腕を組み頭を乗せます。片脚をゆっくり持ち上げ5秒静止し、戻します。逆脚も同様に行います。

中級
初級と同じ姿勢から両脚を持ち上げ5秒静止し、ゆっくり元に戻します。

上級
左足、右腕、頭を持ち上げ5秒静止しゆっくり元に戻します。

右足、左腕、頭を持ち上げ5秒静止しゆっくり元に戻します。
両腕、両脚、頭を同時に持ち上げ5秒静止しゆっくり元に戻します。

グレープバイン
①自然に立ちます。
②左足を右の後方にずらし、体重を左足にかけます。
右足を右側に一歩だし①の姿勢に戻ります。

③左足を体の前を通り右に出し、体重を左足にかけます。
右足を右側に一歩だし、元の姿勢にもどります。

この動きを前後交互に行いながら一方の方向に進みます。
次に体の向きをかえて同じ手順で行います。
慣れてきたら歩幅を大きくします。
スポンサードサーチ
腰痛解消に関連するオススメ記事
- マッケンジー体操!腰痛の知識、原因の解明から実践方法まで
- 座ってできる姿勢矯正法!猫背と腰痛を防ぐ腰椎前彎エクササイズ!
- ロコモティブシンドローム(ロコモ)の評価指標とリハビリテーション
- 骨盤トレーニングの全て!骨盤の知識からトレーニングの方法まで!
- 腰を痛める腹筋運動と腰を痛めない腹筋運動!最新の知見から腹筋を考える!
- 疼痛(痛み)評価とリハビリ:ペインリハビリの基礎の基礎!
- 筋力はあるが体の硬さにより腰が痛い場合のストレッチとトレーニング
- 自分でできる骨盤(仙腸関節)の歪みの診方、ストレッチによる骨盤矯正法!
- 体の部位から考える痛みの原因となる筋肉の見つけ方(体幹、下肢編)
- 自分でできる股関節の痛み解消法!筋肉別トリガーポイントのほぐし方、緩め方!
自分でできる腰背部痛解消法!筋肉別トリガーポイントのほぐし方、緩め方!
呼吸療法認定士の資格を取りたい方は必見
呼吸療法認定士の資格勉強は隙間時間にするのがコツです。呼吸療法認定士 eラーニング講座
スキマ時間勉強ならリハノメ
PTOTSTのためのセミナー動画が見られます。各分野のスペシャリストが登壇しているので、最新の知見を学びながら臨床に即活かす事が可能です。
セミナーあるあるですが、、、メモ取りに夢中になり聞き逃してしまった。
なんてことはなくなります。何度でも見返す事が可能だからです。
高額なセミナー料+交通費、昼食代を支払うよりも、スキマ時間を見つけて勉強できる「リハノメ」を試してみるのも良いのではないかと思います。
臨床で差をつける人は皆隠れて努力していますよ。
長い期間で契約したほうが、月額が安くなります。
PT.OT.STのための総合オンラインセミナー『リハノメ』
PTOTSTが今より給料を上げる具体的方法
転職サイト利用のメリット
何らかの理由で転職をお考えの方に、管理人の経験を元に転職サイトの利用のメリットを説明します。転職活動をする上で、大変なこととして、、、
仕事をしながら転職活動(求人情報)を探すのは手間がかかる
この一点に集約されるのではないでしょうか?(他にもあるかもしれませんが)
管理人は転職サイトを利用して現在の職場に転職しました。
コーディネーターの方とは主に電話やLINEを通してのコミュニケーションを中心として自分の求める条件に合う求人情報を探してもらいました。
日々臨床業務をこなしながら、パソコンやスマホで求人情報を探すというのは手間ですし、疲れます。
そういう意味では、転職サイト利用のメリットは大きいと考えています。
転職サイト利用のデメリット
デメリットとしては、転職サイトを通して転職すると、転職先の病院や施設は紹介料(転職者の年収の20-30%)を支払うことです。これがなぜデメリットかというと、転職時の給与交渉において、給与を上げにくいということに繋がります。
それでも、病院や施設側が欲しいと思える人材である場合、給与交渉は行いやすくなるはずです。
そういった意味でも、紹介してもらった病院や施設のリハビリ科がどのような現状で、どのような人材が欲しいのかといった情報が、自分の持つ強みを活かせるかといった視点で転職活動を進めていくことが大切になります。
転職サイトは複数登録することも必要
転職サイトは複数登録しておくことが重要になるかもしれません。それは、転職サイトによって求人情報の数に違いが生じることがあるからです。
せっかく転職サイトを利用するのであれば、できるだけ数多くの求人情報の中から自分の条件にあった求人情報を探せる方が良いはずです。
その分複数のコーディネーターの方と話をする必要がありますが、自分のこれからのキャリアや人生を形作っていく上では必要なことになります。
また、コーディネーターの方も人間ですから、それぞれ特性があります。
自分に合う合わないと言うこともありますから、そういった意味でも複数サイトの登録は大切かもしれません。
とにかく行動(登録)!管理人も登録経験あり!転職サイトのご紹介!
ネット検索にある転職サイトの求人情報は表面上の情報です。最新のものもあれば古い情報もあり、非公開情報もあります。
各病院や施設は、全ての求人情報サイトに登録する訳ではないので、複数登録する事で より多くの求人情報に触れる事ができます。
管理人の経験上ですが、まずは興味本位で登録するのもありかなと思います。
行動力が足りない方も、話を聞いているうちに動く勇気と行動力が湧いてくることもあります。
転職理由は人それぞれですが、満足できる転職になるように願っています。
管理人の転職経験については以下の記事を参照してください。
「作業療法士になるには」「なった後のキャリア形成」、「働きがい、給与、転職、仕事の本音」まるわかり辞典
転職サイト一覧(求人情報(非公開情報を含む)を見るには各転職サイトに移動し、無料登録する必要があります)
①PT/OT/STの転職紹介なら【マイナビコメディカル】